「ハンドリング」と聞いて、あなたは何を思い浮かべますか?「曲がりやすさ」と答える方もいれば、「ライントレース性能」と表現する方もいるかもしれません。どれも間違いではないし、むしろそれぞれの視点があって面白い。
そして、私の中にもひとつ、しっくりくる定義があります。それは——カーブを曲がるときの、あの“姿勢の気持ちよさ”。
クルマが自然に身体と一体になって、まるで意志を伝え合っているかのようにスッと曲がっていく感覚。その一瞬の「気持ちよさ」こそが、私にとってのハンドリングの良さなのです。
ハンドリングの定義は人それぞれ

そもそも、多くのクルマ好きは「正しいクルマの動かし方」や「感じ方」なんて、持ち合わせていないものです。サーキットなんて行ったことがないし、高速道路だってこの国では時速120km/hが限界。そんな環境で、クルマの性能をすべて引き出すなんて、正直、できる人のほうが少ないのです。
でも、それでいいと私は思います。自分なりに「楽しい」と感じられること。そして、その楽しさを誰かと共有できて、会話が弾んだり、共感してもらえたりしたら、それが何より嬉しい。それこそが、クルマの世界の豊かさじゃないでしょうか。
世の中のクルマを見渡してみると、メーカーだってきっと、そんなことは十分に分かっているはずです。だからこそ、たとえ一般道であっても、ドライバーが性能の違いを“感じられるように”作られている。
実際、私が「これは楽しいな」と思えたクルマがいくつかあります。たとえば、HONDA CIVIC。そして、Peugeot 308。どちらも、ただ速いとかスペックが高いとかではなく、「走るってやっぱりいいな」と思わせてくれる存在でした。
ホンダ•シビックはハイテクハンドリングマシン
アジャイルハンドリングアシストは気持ちの良いカーブを楽しめる

シビックには、「アジャイルハンドリングアシスト」という機能が搭載されています。最近の電子制御が進んだクルマにはよく見られる仕組みで、特にホンダ車では採用例が多い印象です。
この機能、何をするかというと——カーブの姿勢やステアリングの動きを読み取り、ドライバーの意思を先回りして予測。そして、各タイヤに個別にブレーキをかけて、スムーズにクルッと曲がれるように支えてくれるんです。これがなかなか、楽しい。
ふだんは最小回転半径の大きさにため息をつきがちなシビックですが、このアシストがうまく効いてくると、カーブを曲がるのがぐっと楽しくなります。自分の曲がりたい気持ちと、車の曲がり方のシンクロ、格別です。
アジャイルハンドリングアシストは動きを予測して最適化する

仕組みとしては、アンダーステア(外にふくらむ傾向)なら、内側のタイヤにブレーキをかけて回転を促進。逆にオーバーステア(リアが出る傾向)なら、外側のタイヤにブレーキをかけて姿勢を立て直す。まさに姿勢制御の電子サポーターといったところ。
電子制御による走り、というと、「基礎性能が不十分なのでは?」と疑いたくなる人もいるかもしれません。でも、シビックの場合は違います。土台がしっかりしているからこそ、介入が気持ちいい。システムがスッと入ってきて、カーブでの動きに「クルリ」とした楽しさを添えてくれるのです。
シビックは素性の良さがあってこそ

……なんて言いつつ、「ほんとうに基本ができているのか」と問われると、正直よく分からないところもあります(笑)
でも、じわ〜っと曲がっていくような穏やかなカーブでも、アクセルをオン・オフしても、クルマはきちんと狙ったラインを走り続けてくれる。
この感触は、ニュートラルステアを丁寧に整えてある証拠なんじゃないかと、私は感じています。
アクセルをぐっと踏み込んでいるときや、下り坂の急カーブを駆け抜けるとき。シビックがスイーッと美しく回り込んでくれると、私は思わず頷いてしまうんです。「うんうん、これがアジャイルハンドリングアシストの力かあ」って。
走りを手軽に楽しめて、しかも安全。そんなシビック、やっぱり素敵なクルマだと思うんです。
ハイテクで気持ちの良いハンドリングは正義?

……と、言いたいところなんですが。
じつは私、ちょっと寂しく感じることもあるんです。というのも、ある程度荷重移動を自分でコントロールして、クルマと対話しながら曲がる楽しさを知っている世代だから。
たとえば、峠道の上りと下りでは、クルマの曲がり方はまるで別物。同じステア操作でも、タイヤの状態はガラリと変わり、反応もまったく異なる。そうした違いを肌で感じながら走るほうが、物理法則が身体に沁み込むし運転が上手になる気がするんですよね。
そんな感覚を、今も大切にしてくれるのがプジョーというメーカーでした。……いや、過去形で言ってしまいましたが、今はどうなんでしょうね?
プジョー308SWはアナログ感たっぷりのハンドリング
ローテクの集大成を感じるプジョー

私が惚れ込んだのは、1.5L BlueHDiを積んだモデル。ディーゼルながら排気量を抑えて車重を軽くし、フロントにコンパクトなエンジンをマウント。そのおかげなのか、アンダーステアをきわめて自然に、アナログ的に打ち消すという、実に巧妙なクルマでした。
詳しくは想像を交えつつですが、あの特徴的なトーションビーム式リアサスペンションに組み合わされたタイヤ、きっとネガティブキャンバーがしっかりと与えられていたんでしょうね。旋回中のグリップを最大限に高め、リアの滑り出しやオーバーステアも確実にコントロールしていた——そんなセッティングが想像できる、絶妙な走り味があったのです。
そしてもうひとつ、忘れちゃいけないのがi-Cockpit。あのコンパクトなステアリング、想像以上に切れ込んでるんですよね。たぶん、自分の感覚以上にハンドルを切っていて、だからこそアンダーステアがかき消されて、ニュートラルに近いハンドリングに感じていたのかもしれません。
柔らかい足周りの特性を活かす楽しい車

プジョーというメーカーは、やはり足まわりのセッティングが上手い。特にサスペンションは、柔らかくしなやか。そのおかげで、荷重移動による姿勢変化がとても分かりやすく、自分の操作で“曲がっている”という感覚を楽しめるクルマに仕上がっていました。
中でも、Peugeot 308 SWのカーブ姿勢の気持ちよさは格別。あれは、システム任せにせずともドライバーの意思で曲がれる、“人間主体のハンドリング”を体現した一台と言っても良いかもしれません。なにせ、人が走りながらカーブを曲がる時は、Gがかかる。このかかり方が、車と人とで同じように作り込んでいる。車が曲がる時は、外側に沈み込むのが正解なんです。
「なんでもかんでも電子制御に頼らなくても、こういう走りができるんだぞ」そんな声が聞こえてきそうな、良い意味でのアナログ感が、このクルマの魅力でした。
答えはひとつではない 一長一短の醍醐味

とはいえ、あの柔らかさがもたらす沈み込みは、けっこう深い。特に、ステアリングに触れていない同乗者にとっては、その動きが“怖い”と感じられる場面もあったようです。
その点でいえば、シビックのほうがずっと安心感がある。電子制御のサポートが適切に働き、姿勢変化も穏やかで、誰もが安心して乗れる安定感があります。
つまり——自分で操る喜びをくれるのがプジョー。誰と乗っても楽しさと安心を両立してくれるのがシビック。どちらも、異なるアプローチで「カーブの気持ちよさ」を追求した名車だと、結論づけることができますね。そして、どちらも自分で所有したのだと、私は胸を張るのでした(笑)
![monogress[モノグレス]](https://monogress.com/wp-content/uploads/monogress-car-logo-2.png)


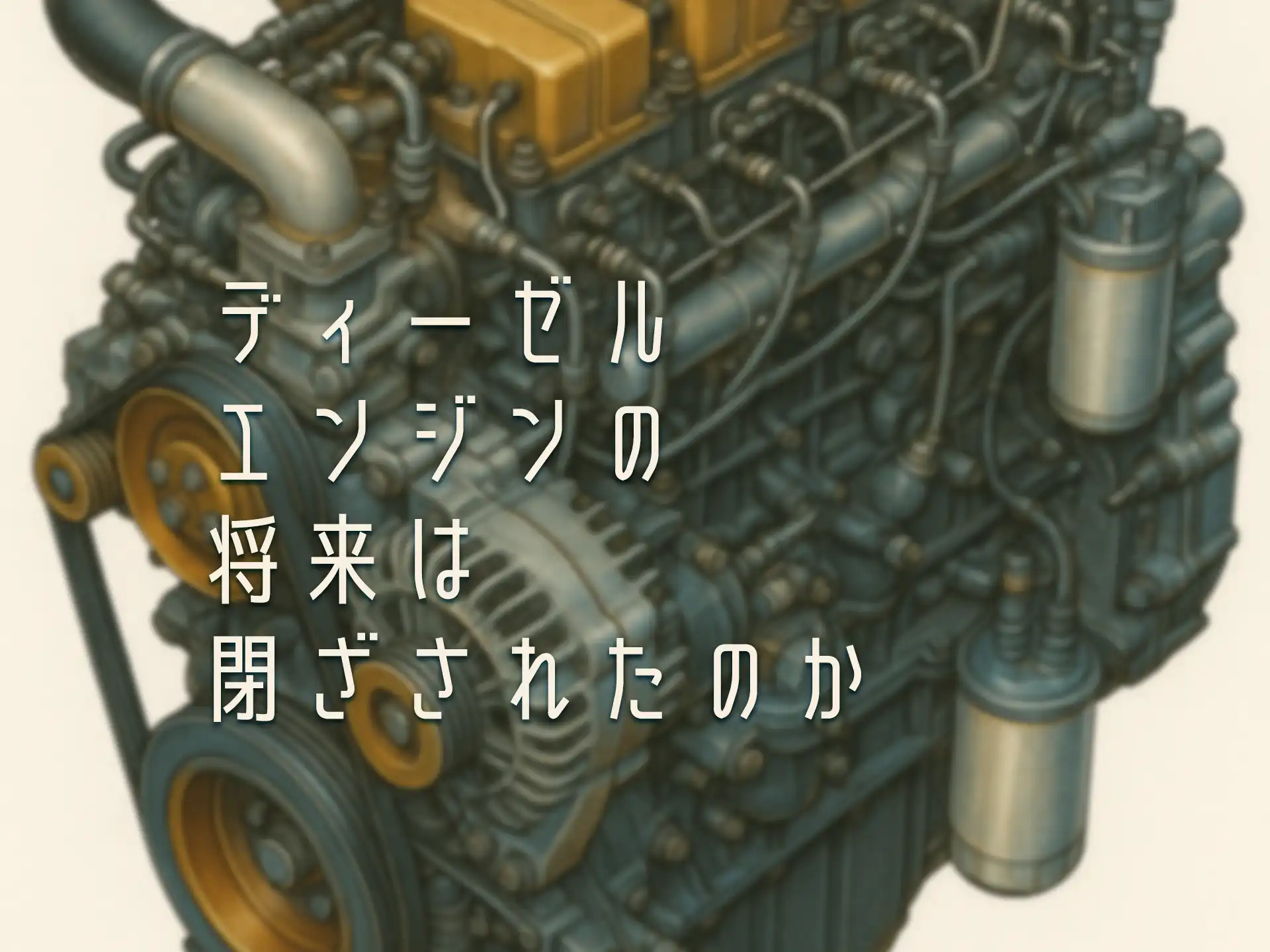











コメントで応援してください!